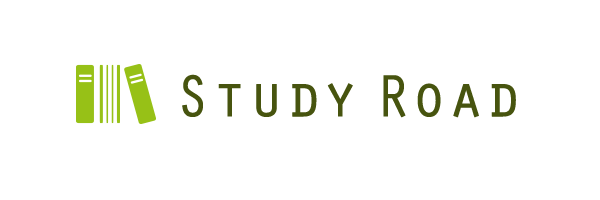はじめに
みなさんこんにちは!
今回は英語の中でも、単語、文法、構文などの総合力や多くの技術的な力が必要とされる長文読解に焦点を当てて勉強法、問題の解き方、練習のためのオススメ参考書を紹介していきたいと思います!
今回紹介することは英語を読むためには必要不可欠な知識であり、私が長期間英語に触れ続ける中で得ることができたものです。英語でしっかり得点したいならこの中の1つでも欠かしてはいけませんので、最後まで読んで各々練習に励んでいただければと思います!

勉強法に関して
これから長文読解の勉強法に関して書いていきますが、長文読解というのは、前提に基本的な単語と文法の知識があるということはみなさんも知っている通りだと思います。ですので、そこが不安な人はまず、単語+文法は標準レベルまで頑張って覚えましょうね!
では、ここからが本題です。英語の長文読解の場合、効率的な勉強をするためにはしっかりとした目的意識を持つことがとても大切になってきます!単語+文法をいくらやっても、なんとなく長文を読んでいるだけでは、いつになっても読解力は成長しません。
英語の場合、意識するべき目標として、速読力と精読力の成長があります。この2つの力の成長を目標とすることを前提として、それぞれの勉強法を紹介していきたいと思います。
1速読力→英語からのイメージの能力の向上

みなさんもご存知かとは思いますが、速読力とはその字の意味のままで、簡単にいえば速く読む力です。
問題なのは、この言葉を知っている受験生は多いのですが、この速読力の上げ方を間違えて理解してしまっている受験生が多いという現状です。まず受験生が読むのを速くしたいと考えてすることが、ガムシャラに問題をときまくることか英語の文を読み漁ることです。
これではいつになっても結果が出ないだけでなく、それを自分の英語力のなさのせいにして、難単語や試験ではほとんど出ない文法事項を覚え始めてしまったりします。
英語が速く読めない理由は、経験のなさ、単語力のなさ、文法の未熟さでは決してありません。
その理由は、英語の意味を考える時に一度日本語に変換してしまっていることにあるのです。少しわかりにくいかもしれないので、図にしてみるとこんな感じです!


図で理解していただけたでしょうか?
では今度は、この直接イメージの力を身につけて速読力を向上させるためにするべき勉強法を紹介していきます!
速読力を上げるための勉強
①音読+シャドーイング
速読力を上げるための勉強をしようと思ったら、まず真っ先に音読とシャドーイングをしましょう!
(シャドーイングというのは、音声CDに少し遅れて音読することで、英語特有の抑揚、リズムを覚えることに非常に役立ちます。ですので、長文読解の参考書は下で説明するCD付きのものを使うことを強く推奨します!)
具体的には、長文読解をした後に、シャドーイング2回+音読3回はしましょう。こうすることで、一度意味を理解した長文の音読ができるので、英語→イメージの練習を効率良くできます。回数をこなしていく中で、できるだけ日本語を頭の中に介在させないように心掛けて音読していきましょう!
また、音読とシャドーイングにはもう一つ有効な効果があります!
突然ですが、みなさんは日本語の文章を読んでいる時(特に小説など)、頭の中でだれかがそれを読んでくれているような感覚になっていませんか。小説などでは頭の中で、異なるキャラクターのセリフは違う声で読まれていると思います。
これはみなさんが日本語を普段から使っているために、無意識に行われていることだと思いますが、英語でもこの状態を作り出せるようになると、読むスピードはグンと上がります。
音読をする習慣を持っておくと、英文が頭に音声として入ってくるようになるため、試験本番でも頭の中で音声が流れているような感覚になり、問題を解くのがかなり楽になります。
以上のように音読には多くの利点が存在しているので、ぜひ今日からでも実践してみてくださいね!
②少し簡単な長文問題
少し簡単な長文問題に取り組むことも、速読力の向上には非常に役立ちます。しかし、しっかりと目標を意識して問題を解いていかなければ、ただ何と無く簡単な英文を読んでいるだけの状態になってしまい、これでは成長は見込めません!
この勉強の時には、英語から直接イメージしていくことを意識して、できるだけ速く読み、問題を解くように、緊張感を持って取り組むことが大切ですよ!
③会話
正直、イメージに関しては会話以上に効果的な勉強法はないかと思います。しかしそこまで身近に外国人がいるとは限らないので、最後に紹介させていただきました。
なぜそこまで効果的なのかというと、会話は流れが大切なので無意識にでも聞いた英語を早く処理しようとするため、自然に英語→イメージの訓練になるからです。
じゃあ、英会話教室などに通うべきなのか、というとそんなことはありません。実際、私も受験生の時には英語での会話をすることはほとんどなく、その分音読に力を入れることで、その穴を十分に埋めることができました。
2精読力

精読力というのは簡単に言えば、正確に読める力のことです。速読力のように複雑なものではありませんが、精読力の向上には比較的時間がかかるので、我慢強くこれから紹介する勉強法を実践していく必要があります。
精読力を上げるための勉強
精読力の向上に関しては、大きく分けて2つの勉強法がありますので、紹介していきます!
①単語推測
単語推測というのは、その名の通り、単語の意味を推測することです。
では、この単語推測に関してはどんな勉強をすれば良いのかを説明していきましょう。
この勉強に関しては特別なことをする必要はなく、長文読解の勉強の時にあることを意識するだけで良いのです。
突然ですが、みなさんは長文の中に知らない単語が出てきた時、どうしていますか?答えとしては2通りあると思います。
①その単語を含む文を飛ばし読みする。
②その単語の意味を文脈から推測する。
もうわかった方もいると思いますが、単語推測の勉強というのはこのうちの②を意識するだけで良いのです。
長文内の単語に関しては、受ける大学のレベルが上がるにつれて、難単語が増えてきます。専門的または抽象的な単語です。これを全て暗記でカバーするのは、あまりに大変過ぎます。ですから試験本番で知らない単語に出会った時のために、必ず長文読解の時には②を意識するようにしましょう!
この勉強をするのに役に立つのが、この速読英単語上級編です。
この参考書は単語帳に分類されるものですが、単語を覚える際に長文の中で覚えることに重点を置いており、長文読解の参考書としても使えます。
さらに、単語推測のコツを多く記載してあるため、英語でライバルにさらに差をつけたいと考えている受験生には非常にオススメです!
②構文解釈
次に紹介する勉強法は、構文解釈です。
構文解釈というのは、主語や述語、目的語、補語の識別や、文中の特殊な構文を見抜いて、適切な意味を考えたりとなかなか、長文読解中に取り組むのは難しいと言えます。
しかし、構文解釈は適切な参考書を使えば、短い時間でマスターできるものでもあります!そこでここでは、私が構文解釈の勉強で使った2冊の参考書を紹介したいと思います!
それは…
英文読解入門基本はここだ!
まず1冊目は「英文読解入門基本はここだ!」です!
この参考書はかなり易しく書かれているため、英語に苦手意識を持つ人、英語の勉強を本格的にスタートしたばっかりの人に非常にオススメの参考書です。薄い参考書なので、早ければ1ヶ月程度でマスターできる内容になっています。
少し簡単過ぎて、拍子抜けするかもしれませんが、基本中の基本なのに意外と見落としやすいポイントがわかりやすくまとめられているため、中級者にもお勧めすることができます!
ポレポレ
オススメの参考書2冊目は「ポレポレ」です!
この参考書は少し難易度は高いため、英語が苦手な人はまず「基本はここだ!」を完璧にしてから取り組むことをお勧めします。
50個の文章の中で、受験では必須の構文解釈の知識、技術、コツが詰め込まれており、この参考書を完璧にすれば、もう構文解釈で悩むことはなくなるでしょう!
英語が得意な人でもう1ステップ上に行きたいと感じている方には、本当にお勧めな参考書です!
問題を解くときの対策
ここからは、実戦でも使える、問題を解く時のテクニックを紹介していきます!

基本編
まずは基本編。どのレベルの受験生であっても必ずしてほしいことです。
・本文前の説明は熟読
本文前の説明は、日本語で書いてる場合と英語で書いてある場合、がありますが、どちらにしてもその後に続く本文の内容に大きく関わってくる可能性があります。ここで、時間を節約することは後々自分の首を絞めることになるので、しっかり熟読しましょう!
・問題を先に見る
問題を先に見ることで、本文中のどこが該当範囲なのかの判断が付きやすくなり、余計な読み直しによる時間の浪費を防ぐことができます。長い長文で、非常に役立ちます。解答に必要な箇所を忘れないように印をつけておきましょうね。
・指示語、接続語にチェック
長文を読んでいく中で、指示語と接続語は非常に重要です。
指示語というのは、this,that,itなどのことで、接続語は、however, but,for exampleなどのことです。
これらの単語にはチェックして、指示語なら何を指示しているのか、接続語からはそれぞれの文のの関係性(下で詳しく書きます)を考えながら読み進めていきましょう!
・問題文と本文の交互読み→ほとんどの問題が解ける 印づけ
上で言った通り、はじめに問題文には目を通すべきですが、全てを覚えれるわけではないはずです。
そこで、問題文を頭に入れながら本文を読み進め、問題の該当範囲に来たらそこでまた問題文に戻り、解答を考えて書き、そしてまた本文に戻る。この繰り返しで問題を解いていくのが時間的に最も速く解答できる取り組み方です。
はじめは慣れが必要かもしれませんが、少しずつ練習で身につけていきましょう!
応用編
ここでは難関大を受験する方向けの応用編を紹介していきます。少し難しいかもしれませんが、難関大受験では必須の知識ですので、ぜひ覚えておいてください!
・各段落の関係を考える。(論理と時系列)

上でも少し触れましたが、接続語を利用したり、段落ごとのポイントを押さえることで、各段落の関係性を考えることが大切になってきます。
各段落の関係性を知ることは、論説文では論理的な意味(筆者の主張、主張の根拠、具体例)を知ることになり、小説では物語のストーリー展開や時系列を把握することになります。
英語では、筆者は基本的には自分の主張を最初の段落に置きます。しかし、難関大で出題される問題は、いきなり具体例を持ってきたり、中盤でいきなり反対の主張の具体例を入れたりと受験生を困惑させる問題であることが頻繁にあります。
小説に関しては、基本的には時系列に沿って進んでいくのが日本語でも英語でも当たり前ですよね。(最近話題の「君の膵臓が食べたい」でも始まった途端にいきなりヒロインが亡くなってしまったりはせずに、主人公との出会い、交流を経て感動のラストを迎えますよね。)
しかし、難関大で出題される英語の小説問題では、時系列がぐちゃぐちゃになっている問題があります。いきなり回想に入ったり、結末が最初に書かれていたりです。
これらを見抜くためにも各段落の関係には注意して読んでいきましょう。
・論説文に関しては筆者の主張を読み解くことを意識、小説に関しては登場人物の視点と感情の変化に気を付ける。

これはもうこのままですね。
結局、論説文というのは筆者にある「主張」があるから書かれているのであり、そこへ導くために問題が出されているのです。その「主張」さえわかってしまえばもう解けたも同然なのです!だから、論説文を読むときは常に「主張」を探すことを意識しましょう!
小説では、それぞれのキャラクターの感情が急激に変化(嫌い→好きのように)するポイントがどこかにあります。そのタイミングを見逃すと、重大な誤読(嫌いだったはずなのに最後に結婚したとか)をしてしまうかもしれません。ですから、小説を読むときは登場人物の感情の変化に気をつけて読んでいきましょう!
オススメ参考書(長文読解)
では、最後に長文読解に役立つ、オススメ参考書を紹介していきます!
長文読解の参考書に必須なのはCDが付いているということです。その理由は上でも書いた通り、音読+シャドーイングのためです。
それを満たした上で、その中でも私がオススメするのは、
〜英語長文レベル別問題集〜
この参考書は東進から出ているため解説の詳しさ、わかりやすさ、丁寧さ、においてバランスが良く、かつ問題数も各レベルで取り組むべき適切な問題数になっているので、使い勝手が非常に良いです。
自分の英語の力に合わせたレベルから始めることができる点も素晴らしいですね。最後にそれぞれのレベルの目安をまとめておきます。
| レベル | 目安 |
| 1 | 中学〜公立高校受験レベル |
| 2 | 公立・私立高校合格レベル |
| 3 | センター試験(基礎)レベル |
| 4 | センター試験・中堅私立大学レベル |
| 5 | 有名私大・国公立大レベル |
| 6 | 難関私大・難関国公立大レベル |
最後に
ということで、今回は英語の長文読解に関することを書いてきました。長い記事になってしまいましたが、どれも大切なことなので、忘れずに今後の勉強に役立ててもらえたら嬉しいです!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
この記事が「ためになった」「面白かった!」と思った人はこちらをクリック!!
現在、家庭教師の募集も行っています!気になった方、体験授業の申し込みは下の記事からお願いします!(残り1人分の空きしかありません。体験授業のお申し込みはお早めにお願いします。)