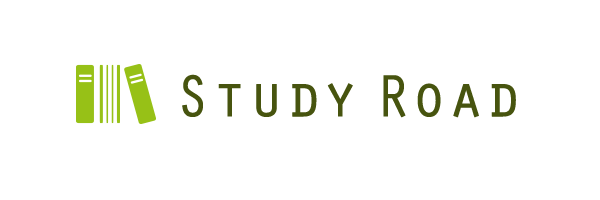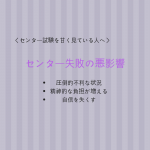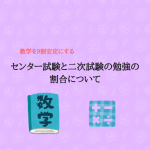受験生の悩み
「センター試験の対策っていつから始めたらいいんだろう?」
この疑問は多くの受験生が持っている悩みです。
そして、センター対策のタイミングを誤ってしまうとセンター試験の結果だけでなく、その後の受験全てに悪影響が出てしまいます。(センター失敗の悪影響についてはこちらから)
だからこそ対策の時期はしっかり考えていかなければなりません。
そこで今回はセンター試験で800点以上を獲得した僕が、受験生を2パターンに分けて、それぞれの適切な対策時期を解説したいと思います。
その2パターンとは、
- センターの配点が高く、重要度が高い場合
- センターの配点が低く、重要度が低い場合
です。
また、二次試験で使用する科目なのか、そうでないのかによっても対策時期は変わってきますので、別々に解説していきたいと思います。
センターの配点が高い場合
二次試験で使用する科目
この場合の適切な対策開始のタイミングは11月半ば〜12月はじめです。
「はやっ!」と思った方もいるかもしれません。しかしそのくらいセンター試験の結果は重要なんです。
<参考記事>

「二次試験で使う科目なら、センターは余裕っしょ」と甘くみていると、痛い目を見ます。(僕の友人にもたくさんいました。)
実際にやってみればわかりますが、問題形式が変更されると、対応するのにある程度の時間がかかります。
さらに、配点が高い場合、安定した高得点が必要ですので、ここは余裕を持った時間配分が大切です。
二次試験で使用しない科目
これが最も時間を使うべきパターンです。
11月中には本格的に対策を始めましょう。
特に、理系における地歴公民や文系における理科は多くの受験生が対策不足で臨みます。
逆に言えば、ここで落とさなければ他の受験生に差をつけることが出来るのです。
多少、他の科目の時間を削ってでも、これらの科目の対策に時間をかけましょう。
センターの配点が低い場合(難関大など)
二次試験で使用する科目
ここは一番対策をおろそかにしがちな部分だと思います。
しかし、遅くても12月半ばからは対策を始めるべきです。
「普段から難しい記述問題を解いてるし、センター対策なんていらないでしょ。」
そう考えている難関大志望者は多いと思います。
しかし、センター試験には記述式とは異なるクセがあり、またそれを攻略するコツもあります。
このコツを知っているかどうかで、結果は大きく変わってきます。
僕自身も、受験生の時に数学の記述式とマーク式のギャップに苦しみました。1月から対策していては遅かったと思います。
必ずクリスマスの前にはセンター試験対策に移りましょう!
二次試験で使用しない科目
上でも述べているように、理系における地歴公民と、文系における理科の対策は受験生がおろそかにしがちです。
ですのでここはしっかり、12月初めには対策を始めることをオススメします。
僕は理系で地理選択でしたが、12月はじめには対策を始めて、本番形式の問題を30回は解いたと思います。
その結果、苦手だった地理でも89点を取ることが出来ました。(詳しい勉強法は下のカードから飛べます。)

「得意科目を伸ばすよりも、苦手科目を伸ばす方が圧倒的に簡単」
これは受験全般で言えることですが、センター試験では特に重要です。忘れずに。
まとめ
ということで、今回はセンター試験の対策を始める時期について、解説してきました。
表でまとめると、
| 配点 | 二次試験 | 時期 |
| 高い | 使用 | 11月半ば〜12月初め |
| 使用しない | 11月半ば | |
| 低い | 使用 | 12月半ば |
| 使用しない | 12月初め |
といった感じです。
もちろん個人差はあっていいと思いますが、自分を過信しすぎずに、余裕を持って対策を始めましょうね!
この記事が「ためになった」「面白かった!」と思った人はこちらをクリック!!
現在、家庭教師の募集も行っています!気になった方、体験授業の申し込みは下の記事からお願いします!(残り1人分の空きしかありません。体験授業のお申し込みはお早めにお願いします。)