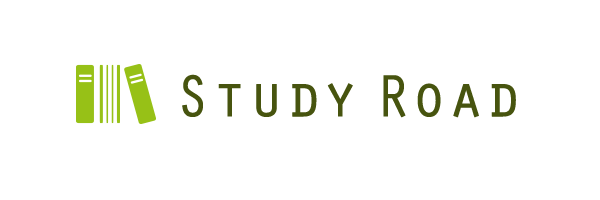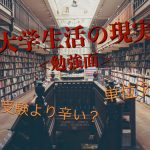はじめに
みなさんこんにちは!いと(@StudyRoad)です。
今回は理系早稲田生が文系・理系を問わず数学の偏差値を65まで上げる勉強方法&参考書を紹介していきたいと思います!
ここでまず、なぜ偏差値65までなのかと言うと、今回ご紹介する方法を実践した時に最低でも到達できるラインが偏差値65だと思ったからです。
ネット上には、読者を増やすために闇雲に高い数字をだし、期待を煽るものの、実際に紹介する勉強法はなんだか抽象的(はっきりしていない)、または極端な努力論(もちろん努力は大切ですが…)になってしまってる記事が山ほどあります。。これらの記事を読んだところで、正直結果はほとんど出ないと思います。
ということで、今回は少し地味かもしれませんが、結果が確実に出る勉強法を紹介したいと思いますが、注意点が1つだけあります。その注意点とは、今回紹介する勉強法は私がいくつもの勉強法を試す中で見つけた最も効率的なものですが、ある程度の時間と労力はもちろんかかるという事です。最低限の努力もなしで、成績を上げることは出来ませんからね。
これから紹介する勉強法を実践する事でみなさんに「努力が実る喜び」を感じてもらえれば幸いです。
偏差値65までの道のり
大まかなことは以前記事にしているのでご覧ください。

この記事で書いているように数学の成績をあげるためには次の4つのステップがあります。
①基本公式の暗記
②基本問題演習
③入試標準問題演習
④応用問題挑戦(思考力up)
この中で、偏差値65までなら③までを完璧にすることが必須となります。というか③まで完璧なら偏差値70も目前だと言えるでしょう。
①に関しては上の記事で紹介している通り教科書の公式を覚えるだけなので、詳しい解説はしません。②、③に関して詳しく解説していきたいと思います。
②基本問題演習の取り組み方
この段階はわかりやすく言えば、解法暗記ってやつです。具体的に何をするかというと、自分でこれだと決めた基本的な問題集(オススメは後ほど紹介します。)を何度も何度も(少なくても3回)解きまくり、その解法を暗記してしまうだけです。簡単に言っていますが、ここが受験数学では1番大切だと思っています。RPGで例えれば、ここは武器を揃える段階、桃太郎なら犬、猿、雉にきびだんごを与える段階、ポケモンならジムで勝つために野生のポケモンを捕まえてレベル上げをしている段階と言ったところでしょうか。
だからこそここが待ち受けるボス(鬼、ジムリーダー)を倒す、つまり入試標準問題を解くためには1番大切で、最も時間と労力をかける時間だということです。
しかしみなさんは時間の限られた受験生ですのでここに何年もかけていてはいけません。だからこそ私がオススメする解法暗記の方法は「わからなかった、または思い出せなかったらすぐに答えを見ること。」そして、「その答えを目力で破れてしまうくらいに熟読すること。」です。
この方法はすでに推奨している人が多くいますが、なかなか有効な勉強法として定着していません。その大きな原因としては「いやいや、数学は暗記じゃなくて本質的な理解が必要だからこんな方法意味ないよ!」ともっともらしい文句をつけて実践しない人が多いことが考えられます。
しかし、私や過去に指導した生徒の経験からわかったことですが、最初は暗記しようとしても量が多いため、理解は自ずと必要となるので、暗記しようとするだけで問題は全くなく、むしろ文句ばかりを言いながらずっと分からない問題集を見つめている方がはるかに問題であるということです。
桃太郎だって、はじめから武力行使で犬や猿に殴りかかっていき、従わせ、ボロボロになりながら仲間を調達したりはせずに、力が少ないからこそ地道な交渉ときびだんごで仲間を集めていました。ポケモントレーナーだって….(以下略)
数学の成績の伸び悩みを感じている人はまずこの方法を実践してみてください。1〜2ヶ月で目に見える結果が出てくると思います。
②基本問題演習のオススメ参考書
ここでは②基本問題演習のオススメ参考書を紹介しながら実際に私が使ったものに関しては、解説も加えていきたいと思います。各種教科書附属の問題集(4プロセスとか、4STEPなどのはじめに学校で配られるもの)でも十分です。
みんな大好きチャート式シリーズ(青・黄)
青チャートは私が高校生の時も使っていましたが、みなさんの中にも学校で配布されて持っている人が多い参考書だと思います。
この参考書は全国の高校に信頼されてあるだけあって、変なくせのある問題は少なく、入試基本〜標準レベルの問題をしっかり網羅した素晴らしい参考書だと思います。また、例題の難易度をコンパスマークで示してある点も非常に親切だと思います。ただし、基本問題演習で使う場合、注意点があります。それは基本問題演習で使う場合、目的は解法暗記なので章末のEXERCISESは飛ばし、例題のみをとけば十分です。(コンパスマーク5は無視でも構いません。)
意外と少数派?Focus Gold
ほぼ青チャートと同じです。どちらにするかは各自の好みで決めて大丈夫です。
繰り返しになりますが、どの参考書を使う場合でもとにかく何周もして、問題を見た瞬間に解法が思い浮かぶようにしましょう。
③入試標準問題演習の取り組み方
ここでいよいよ①②で集めてきた武器を活用して問題と格闘していく段階です。
この段階では②とは異なり、10分程度は考える時間を設け、どの武器を使うのかをよく考えながら取り組んでいきましょう。
もちろん理想としてはいきなり問題が解けることが理想ですが、なかなかうまくいかない場合がほとんどだと思います。その場合は②で使った参考書を手元に置き、10分程度経過しても解法の流れが思い浮かばなかった時には、その参考書を見ながらでも解き始められれば大丈夫です。
次第に慣れてきて解法がわかってくると思います。一度暗記した解法を駆使して戦うことがわかればここからあなたの数学に対する考え方が大きく変わると思います。
しかし、もし②で使った参考書をみて何も思い浮かばず、手が動かなかった場合は②の解法暗記が不十分であることが原因と考えられます。この場合に自分の才能のなさを原因に決めつけてしまう学生が多いようですが、全く違います。ただの練習不足です。恐れることなく、もう一度解法暗記に戻ってください。解法暗記はそれだけ時間をかける価値のある段階です。
③入試標準問題演習のオススメ参考書
青(黄)チャートとFocusGoldのEXERCISES
②に続いて再登場になりますが、チャートとFocusGoldのEXERCISES部分がこの段階では適切な難易度です。チャートとFocusGoldは難易度も幅広く、使い勝手のいい参考書ですので、夏休み前にぜひ購入を検討してもいいかもしれません。(画像をクリックすると、Amazonのページに移ります。)
コアなファンが多い?1対1対応の演習
これらの参考書も同じく③の段階での最適な難易度です。解説がチャートなどとは少し異なる視点から書かれているため、万人受けはしませんがハマるとすごくわかりやすく感じます。ですので、1度書店で見てみると良いと思いますよ!
最後に
数学は、解法暗記の段階を超えてしまえば、問題を解くのが楽しくなり、自然に論理的に解答を書いていく能力がついてきます。この論理性は日常生活でも大いに役立つものであり、今後の皆さんの人生を豊かにしてくれるでしょう。はじめは大変だと思いますが、ぜひ粘り強く勉強していってください!頑張ってください!
【追記】[独学]私の数学の参考書歴を紹介します。[偏差値70越えまでの道のり]

この記事が「ためになった」「面白かった!」と思った人はこちらをクリック!!
現在、家庭教師の募集も行っています!気になった方、体験授業の申し込みは下の記事からお願いします!(残り1人分の空きしかありません。体験授業のお申し込みはお早めにお願いします。)