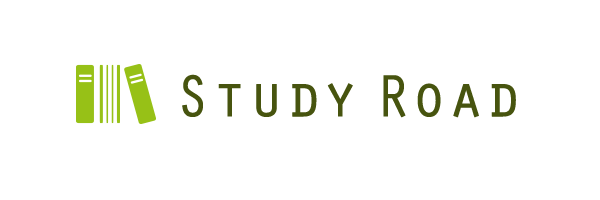はじめに
みなさんこんにちは!いと(@StudyRoad)です。
受験体験記最終回の今回は私が東大を受験したときに体験したことを詳細に書いていきたいと思います。
東大受験は他大学とは異なり、2日間に及ぶ戦いになりますので、自分の気持ちの動きをうまく管理していくことが必要です。ですので、本番の緊張感も伝えていきたいと思います!よろしくお願いします!
東京大学の受験基本情報
| 東京大学の基本情報 | |
| 受験者数 | 約一万人 |
| 受験会場(理類) | 本郷キャンパス |
| 偏差値 | 70以上 |
本郷キャンパスへのアクセスとしては、
- 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅
- 都営地下鉄大江戸線 本郷三丁目駅
- 東京メトロ千代田線 根津駅
- 東京メトロ南北線 東大前駅
- 都営地下鉄三田線 春日駅
これらの駅が徒歩15分圏内に位置しています。
本番当日の本郷キャンパスは本郷通り沿いからは正門からの入場のみが許可されているので、地図で位置を確認しておきましょう!
東京大学試験会場(本郷キャンパス)

(2018年9月24日追記)本郷キャンパスに本郷通り沿いから入れるのは「正門」だけですが、本郷通り以外では「弥生門」の他2箇所の臨時ゲートからも入場可能です(いずれも正門と比べればだいぶ空いています)。臨時ゲートは上の地図に記載されていませんので、近日中に地図を用意して追記します。
↓赤門↓
*本番はここからは入れません。
私の受験対策と科目別対策
私が東大に特化した勉強を始めたのは高3夏休みの中盤からでした。
具体的には長いリスニングや自由英作文などですかね。過去問は10月に入った頃に手をつけ始めました。
ここでみなさんに1つ注意していただきたいことがあります。東大や京大などの同レベルの大学が存在しない大学を第1志望にしていると、割と早い段階で過去問をやり終わってしまい、同レベルの初見の問題を演習することができなくなってしまいます。
ですので、各予備校(河合塾、駿台など)の大学別模試の過去問をどうにか入手しておくことをお勧めします!ただし科目によっては本番の難易度が再現されていないものもあるので、注意しましょう。(特に、どの予備校であっても理科は難しめに設定されていることが多いです。)

英語
東大の英語の最大の特徴は何と言っても、時間に対して問題数が異常に多いことです。私も夏の東大模試の時点では、読むスピードが全く足りずにあたふたしていたら終わってしまいました。。。
設問の特徴としては、上でも述べた、長いリスニングと自由英作文が挙げられます。特にリスニングには慣れが必要であり、私がリスニング対策として実践していた勉強法はなんといっても音読とシャドーイングです。冗談抜きで、速読英単語は各100回は音読とシャドーイングをしていたと思います。他にもたくさんの参考書を用いて、リスニングは対策していました。それらについてはまた今度ゆっくりお話しできたらと思います。
目標としては、120点中60点から70点台になると思います。
▼実践した英語対策


数学(理系)
150分で大問が6つ。1つにかけられる時間は25分と普通くらいですが、問題の重厚さはさすが東大といったところ。
東大の数学はここ数年難易度が大きくブレています。5年ほど前までは5割取れたら大喜びしていいと言われていましたが、2017年度は少なくとも6割は取らなければならない問題構成でした。
2018年度でまた難易度がぐっと上がりましたが、今後の展開は全くわかりません。
対策としては、正直、運もありますが、私の場合は過去20年ほど出続けていた確率分野を固めて行きました。(しかし本番では出ませんでした涙。)
1日目の最終科目ですので、できなくても次の日に引きずらないことが1番大切ですよ。
▼実践した数学対策



理科(物理、化学)
まず全体として、時間は150分で、大問が各3つずつあります。
物理
物理に関しては、東大理系の中では比較的点を取りやすい科目になっています。年にもよりますが7、8割狙える年もあります。
しかし、物理は問題の性質上、雪崩式に点を失いやすい科目でもあります。絶対に簡単なミスから崩壊しないようにしましょう。個人的な意見ですが、意外とここが一番合否を分けていると思います。
化学
化学に関しては、数学と同じく年によって、難易度のばらつきが大きいですが、全体的には設問の問題文が非常に長く、また問題も普通の大学とは異なり具体的な実験のようなものが多く、慣れないうちは問題の意味がよくわからないまま終わってしまうこともあります。
しかし以外と慣れてくると問題中に答えが隠されていたりして、簡単に解けるものもいくつか見つけることができるようになってくると思います。当たり前ですが過去問でよく演習しましょう!
よく問題になる時間配分に関しては、ほかの人の意見を取り入れつつも、最終的には自分で決めるのがいいと思います!(ちなみに私は、はじめの60分で物理を終わらして、残りで化学をやっていました。これでも化学は終わらない時もありました。。。)
▼実践した物理&化学対策




国語(理系)
100分で現代文(評論文)、古文、漢文が出題されます。
現代文に関してはもう正直、採点基準もよくわかっていないので過去問で練習あるのみかなと思います。(私は他に参考書も使っていたので、それらに関してはまた別の記事で紹介したいと思います。)
ということで現代文は置いといて、理系が戦うべきなのは、古典でいかに稼ぐかという勝負です。古典は他の理系科目と比べると基本知識さえ覚えてしまえばある程度点が取れるようになります。ですので暇な時などには、古文単語や漢文の句法の暗記を進めましょう!
地理B
▼実践した地理B対策

受験前日に関するアドバイス
私からみなさんにアドバイスしたいことは2つあります。受験はまだ先かもしれませんが、とても大切なことなので頭に入れておくことをお勧めします。(これらはどの大学を受験するときにも当てはまる事なので、他の受験体験記にも書いてあります。見たことあるという方は、飛ばして読んでもらえると幸いですm(._.)m)
2.寝られない時の対策をしておく。
まず1に関してですが、受験前日の受験会場の下見をする事で当日余計な心配をする事なく試験に集中出来るようになります。
下見というと会場をちらっとみれば良いような気がするかもしれませんが、それではほとんど効果がありません。
下見をする目的は家(ホテル)から試験を行う教室までの自分が通る道を確認する事です。
ですので、自転車で行く人は駐輪場、車で送ってもらう人はどこで降りるのか、電車で行く人は駅のどの出口で出るべきなのかなどを確認すると良いと思います。(田舎に住んでいる人向けの話になりますが、東京などの都会の地下鉄の駅の出口は無数に?あり、都会初心者には迷路にしか見えません。)
次に2に関してですが、試験の前日というのは想像しているよりも遥かに緊張し、意外と寝られないものです。
そのため、寝るための方法を自分で編み出しておくことが大切になります。そうしないと、寝られない→睡眠不足で頭が回らないかも→あ〜早く寝なきゃ!→でも寝られない(以後無限ループ)このような悪循環に陥ります。
だからこそ!自分なりの対策を練っておきましょう。(私の場合は、最低でも寝ていなきゃいない時間の2時間前には布団に入ったり、大量に持ち込んだホットアイマスクを使ったりしてました。)
1はどこのサイトでも言っていることですが、意外と2に関してはあまり言及されていないので注意!!
東京大学受験体験記
ここからが東京大学受験体験記になります。東大受験は2日間ですので、そこでの生活になれるように私の場合は受験1日目の前々日に東京入りをしました。ですので受験前日は丸1日東京で過ごし、雰囲気に慣れました。こうすることで、本番での緊張を最小限に抑えることができますよ!お勧めです!!

1日目
しかし、これでもやはり前日は緊張であまり眠れませんでしたが、最低限の睡眠はとって、当日は朝6時ごろに余裕を持って起床しました。
ゆっくりとお風呂に入り、朝食を食べに食堂へ向かうと予想外に人がたくさんいたため食堂に入れず、仕方なく一応買っておいたおにぎりで朝食を済ませて、開門20分前頃には門に到着するようにホテルを出ました。
正門前に到着するとそこには数多くの受験生、親たち、予備校関係者、門の目の前には大きなカメラを持ったテレビ局の人と大にぎわいです。


今までの受験では経験することのなかった異様な雰囲気に少し驚きながらも、予想はしていたことなので、早めに落ち着きを取り戻し、古文の単語帳を確認していました。(意外と正門前の道は狭いので、列を少し乱すと、他の歩行者の方々に迷惑になってしまい、東大アメフト部の人たちに怒られます。。)
しばらくすると門が開き、入場が始まりました。私は浪人するつもりはなかったので、予備校の資料は全く受け取りませんでしたが、必要な人も帰りにもらえばいいと思います、余計な荷物になりますので。(2018年度は開門は予定時間ぴったりに行われましたが、年によっては少し早めに開ける事もあるみたいなので、早めに行っておくと良いでしょう。)
第1科目:国語
という事で大きなトラブルもなく入室し、国語の準備をして監督官を待ち、1科目目の国語が始まりました。
もともと、国語は差がつきにくいということは聞いていたので、あまり緊張せずに問題に挑めました。例年より漢文が難しく少し焦りましたが、大きなミスはなく無難に終え、一旦ホテルに帰りました。
(東大受験では、1科目ごとの間隔が長いため、ホテルを近くにとっておけば一旦ホテルに帰り、周りに流される事なく勉強に集中することができますよ!各大学の受験で私が宿泊したホテルはこちらの記事で紹介しています。)
昼食を取った後、開始時間の30分前には大学に戻り、数学の開始を待ちました。寸前までほぼ確実に出題される確率分野の確認をしていました。
第2科目:数学 〜確率が…〜
しかし、いざ数学が始まり問題を確認するとどこにも確率の問題はありませんでした。。。
その時は本当にびっくりしすぎて、少し笑ってしまいました。
「あんなにやったのに。。。」
しかし、いつまでも引きずっていても仕方がないので、とりあえずどう見ても簡単そうな第1問から取り掛かり、結果的には2完と部分点かなというところで1日目の試験が終わりました。
1日に受けた科目数で言えば、今までの受験より少ないですが、やはり精神的にはヘロヘロになってホテルに帰りました。ホテルで今まで何周もした数学の参考書を見るとなんだか少しあっけないような寂しいような嬉しいような複雑な気持ち(みなさんも経験すると思います。)になりましたが、早々に切り替えて理科と英語の確認に入りました。
少し眠気も感じていたので早めに勉強は切り上げ、11時ごろには就寝したと思います。
2日目
1日目と同様に6:00には目覚め、準備をした後、2日目は開門予定時刻ちょうどに正門に到着するようにホテルを出ました。個人的にはこっちの方が、寒い中立って開門を待つ必要はないので、ストレスはないかなと思います。

2日目も特に大きな問題はなく教室に入り、開始を待ちました。
第3科目:理科 〜まずまずの出来〜
2日目1科目目の理科が始まり、まずは計画通り物理から取り組みました。第1問の力学は例年よりも少し簡単でしたが、第2問の電磁気のコンデンサーの問題が少し難しく、第3問は予想していた波動ではなく、熱力学でしたが、なんとか6〜7割をもぎ取り、化学に移行しました。
化学は東大にしては珍しくアミノ酸関連の問題が出ていましたが、割と得意なとこでもあったので理科は全体的に良く出来たという実感の中終えることができました。
第4科目:英語 〜全然過去問と違う!〜
またまた1日目と同様ホテルに一旦戻り、リスニングを中心に確認作業をしました。後1科目で長い長い地獄の受験生から脱出できるということでよく集中することが出来ました。
時間に余裕を持って大学に戻り、英語が開始されました。
早速、問題を確認すると、(東大受験生がおそらく全員驚いたことと思いますが)なんと自由英作文が1つになり、和文英訳の問題が出題されていました。
さらにサプライズはこれだけではなく、リスニング問題の選択肢が4つから5つに、通常記号問題であった第5問が記述式に変更されていました。
ただでさえ日本最難関の東大英語がより残酷な難しさに進化していたのです。
あまりの変更点の多さに困惑しながらも、問題を解き進み、最後に意味不明な自由英作文(シェイクスピアの一節の感想文)をザーーーっと書きあげて、私の長く苦しい受験生活が終わりました。

最後に 〜受験を経験して〜
以上で、東大受験体験記は終わり、私の受験校4つの体験記が書き終わったので、ここで最後に大学受験全体を通しての感想みたいなことを書いていきます。これを読んでいる人のほとんどは受験生だと思うので、モチベーションの維持に役立てばいいなと思います。
私にとって受験は99%辛い思い出です。もう2度としたくない。私はもともと勉強があまり好きではなかったし、高2の終盤からというスタートの遅さからくるプレッシャーの大きさも原因の1つだと思います。
ここで、普通なら「まあ終わってみれば良い思い出です。みなさんも頑張りましょう!」みたいな感じで締めるものです。(確かにこの時期の友人との思い出は心に残りやすいですが)しかし、個人的にこの締めは好きではないので、もう少し自分の意見を書いてみます。
受験生の皆さんは今本当に辛い思いをしていると思います。私が皆さんにお願いしたいのは、絶対に大学受験に後悔を残して欲しくないということです。
個人的な意見ですが、大学受験で人生はそんなに大きく変わったりはしないと思います。何年もかけて勉強したことは、たった1日、2日の試験の出来だけでは決して評価できません。
1番大切なのは、目の前の目標に向かって突っ走ることができるかどうかです。その瞬間瞬間を全力で突っ走ることができれば、万が一失敗しても後悔は残らないものです。そして全力で走りきった思い出は絶対その先の人生で役に立ちます。
長々書いてしまいましたが、受験生の皆さんは後悔なく受験を終われるように、勉強頑張ってください!!応援しています!!




この記事が「ためになった」「面白かった!」と思った人はこちらをクリック!!
現在、家庭教師の募集も行っています!気になった方、体験授業の申し込みは下の記事からお願いします!(残り1人分の空きしかありません。体験授業のお申し込みはお早めにお願いします。)